大学入学共通テスト(理科) 過去問
令和4年度(2022年度)追・再試験
問91 (物理(第4問) 問4)
問題文
図2のようにX線管のフィラメント(陰極)・陽極間に高電圧を加え、陰極で発生した電子を陽極の金属に衝突させるとX線が発生する。図3は、陽極にモリブデンを用いた場合の、各電圧ごとに発生したX線の強度と波長の関係(X線スペクトル)を示している。たとえば、両極間の電圧が35kVの場合には、図のC点を最短波長とする連続スペクトルが得られた。また、連続的なスペクトルの中に鋭い二つのピーク(a)、(b)も観測され、このピークの波長は電圧によらない。
図3の結果を見たPさんとQさんが会話を始めた。ここで、プランク定数をh,光速をcとする。ただし、PさんとQさんの会話の内容は間違っていない。
空欄( オ )・( カ )に入れる記号と語の組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
Qさん:図3を見ると、二つの鋭いピークの波長は、電圧を変えてもまったく変化していない。二つのピーク(a)、(b)のうち、X線の光子のエネルギーが小さいのは( オ )の方だね。これらの二つのピークが現れるのは何に関係しているんだろう。
Pさん:陽極金属の種類を変えてみよう。そのとき、X線のピークの波長は変化することがわかっている。つまり、このX線のピークは陽極金属の特性に関係するようだね。では、両極間の電圧が35kVのとき、最短波長は図3のC点と比べてどうなるだろうか。
Qさん:最短波長は変化( カ )はずだよね。
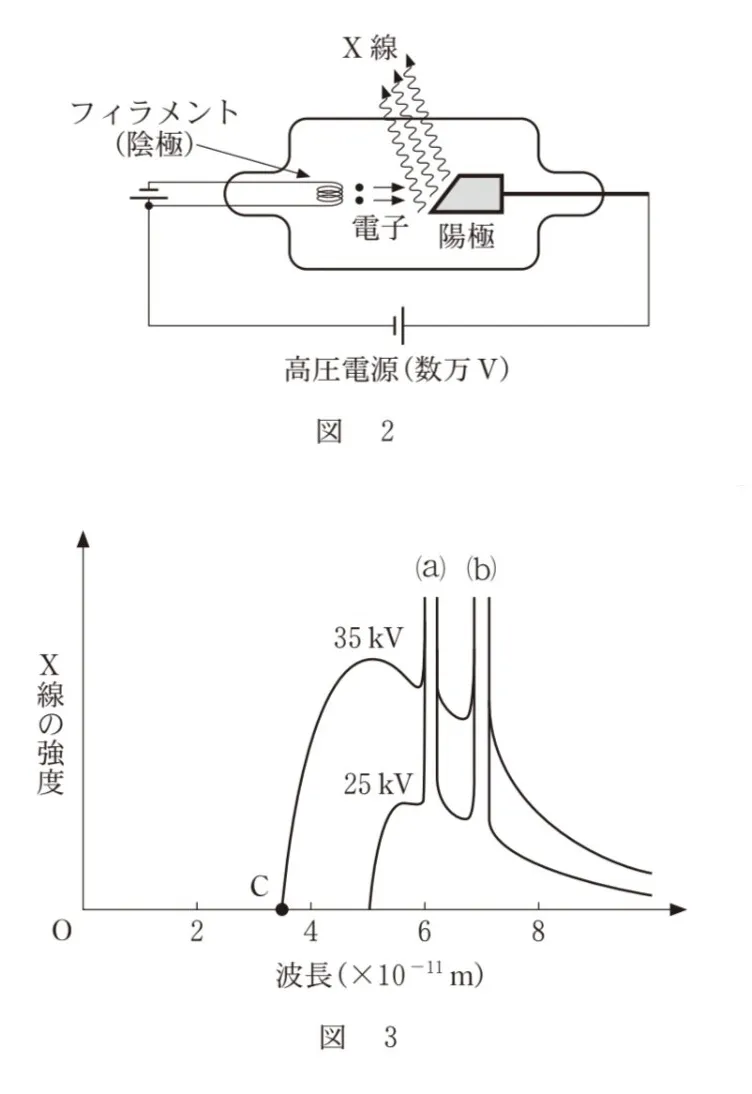
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
大学入学共通テスト(理科)試験 令和4年度(2022年度)追・再試験 問91(物理(第4問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
図2のようにX線管のフィラメント(陰極)・陽極間に高電圧を加え、陰極で発生した電子を陽極の金属に衝突させるとX線が発生する。図3は、陽極にモリブデンを用いた場合の、各電圧ごとに発生したX線の強度と波長の関係(X線スペクトル)を示している。たとえば、両極間の電圧が35kVの場合には、図のC点を最短波長とする連続スペクトルが得られた。また、連続的なスペクトルの中に鋭い二つのピーク(a)、(b)も観測され、このピークの波長は電圧によらない。
図3の結果を見たPさんとQさんが会話を始めた。ここで、プランク定数をh,光速をcとする。ただし、PさんとQさんの会話の内容は間違っていない。
空欄( オ )・( カ )に入れる記号と語の組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
Qさん:図3を見ると、二つの鋭いピークの波長は、電圧を変えてもまったく変化していない。二つのピーク(a)、(b)のうち、X線の光子のエネルギーが小さいのは( オ )の方だね。これらの二つのピークが現れるのは何に関係しているんだろう。
Pさん:陽極金属の種類を変えてみよう。そのとき、X線のピークの波長は変化することがわかっている。つまり、このX線のピークは陽極金属の特性に関係するようだね。では、両極間の電圧が35kVのとき、最短波長は図3のC点と比べてどうなるだろうか。
Qさん:最短波長は変化( カ )はずだよね。
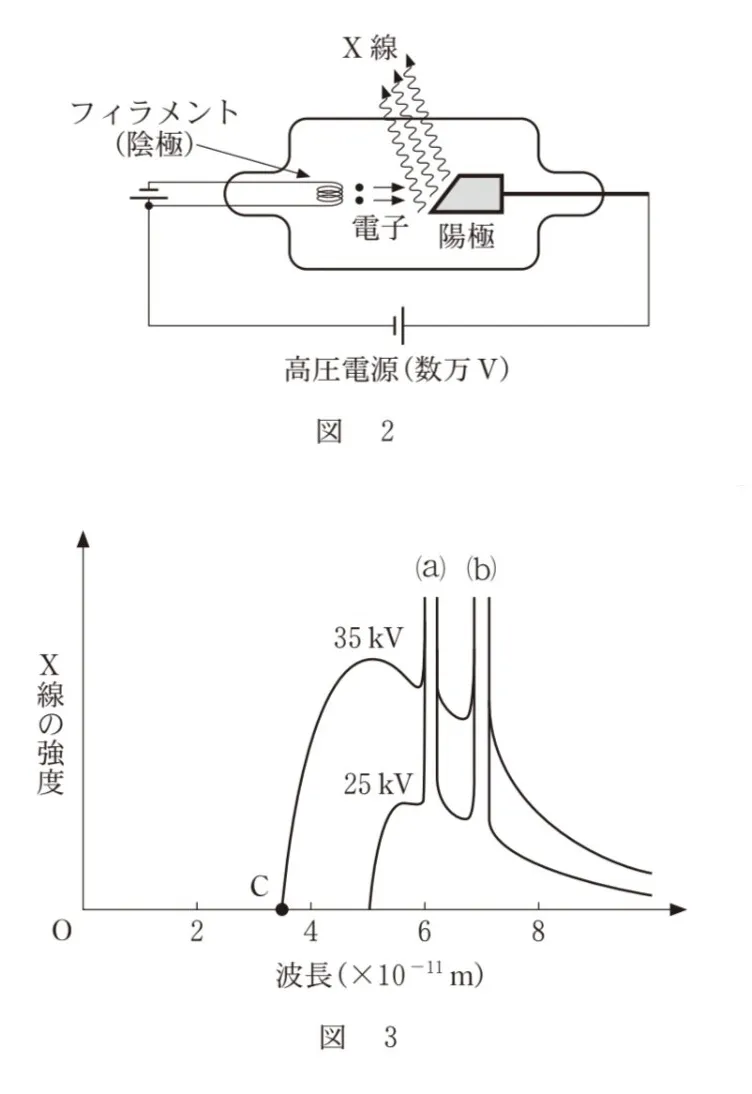
- オ:(a) カ:しない
- オ:(a) カ:する
- オ:(b) カ:しない
- オ:(b) カ:する
正解!素晴らしいです
残念...

この過去問の解説 (2件)
01
X線の光子のエネルギーが小さいのは(b)の方であり、
陽極金属の種類を変えても、
最短波長は変化しないです。
光子の持つエネルギーは
E=hc/λ
と表されます。
したがって、波長が大きい(b)の方がエネルギーは小さくなります。
また、エネルギー保存則より
電子の運動エネルギーが光子のエネルギーに変換されるとき、
つまり、 eVとhc/λが等しいとき、
最短波長になります。
よって、
eV=hc/λ
λ=hc/eV
となります。
この式から最短波長は電圧にのみ依存することが分かります。
そのため、陽極金属によって最短波長は変化しません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
光子のエネルギーは
hc/λ
で与えられます。
つまり、波長にエネルギーが反比例するため、波長が大きい(b)の方がエネルギーは小さくなります。
また最短波長は光子のエネルギー保存則より
電子の運動エネルギーeVと光子のエネルギー hc/λとが等しい時に最短波長になるので
eV=hc/λ
λ=hc/eV
となり、陽極金属によって変化しない、ことがわかります。
X線のエネルギーがhc/λであることをきちんと覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問90)へ
令和4年度(2022年度)追・再試験 問題一覧
次の問題(問92)へ